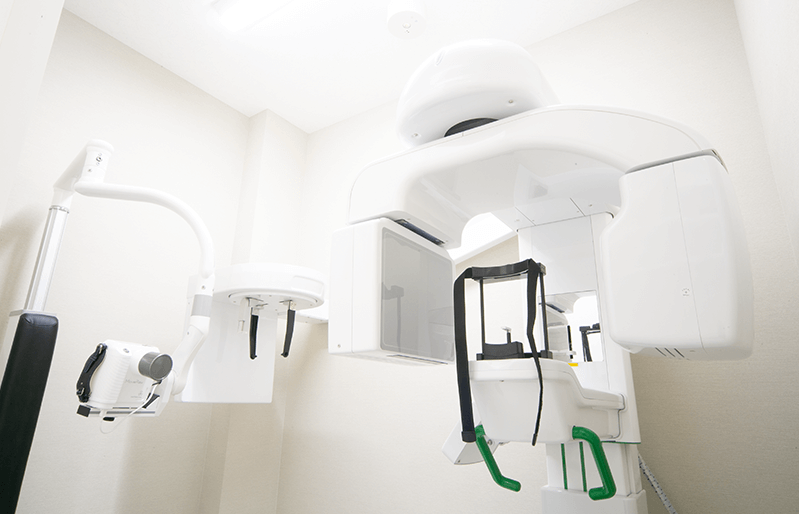お口と身体の健康を守る第一歩は、かみ合わせについて正しく理解することから始まります。
「良いかみ合わせ」とはどのような状態?
「良いかみ合わせ」とは、単にすべての歯が接触していれば良い、というわけではありません。
以下のようないくつかの条件が満たされている状態を指します。
良いかみ合わせの条件
- 均等な接触:上下の歯が、奥歯から前歯まで、均等な力でバランス良く接触している。
- 安定した顎の位置:口を閉じた時に、顎の関節が正しい位置に自然と収まっている。
- スムーズな動き:食事や会話の際に、顎が引っかかったり、ずれたりすることなく、スムーズに動かせる。
- 負担のない状態:歯や歯茎、顎の関節、そして筋肉に過度な負担がかかっていない。
これらの条件が一つでも崩れると、かみ合わせのバランスは少しずつ乱れていきます。
なぜかみ合わせは悪くなるのか?
かみ合わせのバランスが崩れる原因は、一つではなく、様々な要因が複合的に関係しています。
かみ合わせが悪くなる原因
- 歯並びの乱れ(不正咬合):元々の歯並びが乱れている場合、正しく噛むこと自体が困難です。
- 歯の喪失:抜けた歯をそのままにしていると、隣の歯が倒れ込んだり、向かいの歯が伸びてきたりして、全体のバランスが崩れます。
- 不適合な詰め物・被せ物:過去の治療で入れた詰め物や被せ物の高さが合っていないと、そこだけが強く当たるなど、かみ合わせのズレを生じさせます。
- 親知らずの影響:親知らずが斜めや横向きに生えることで、手前の歯を押し、全体の歯並びと噛み合わせを乱すことがあります。
- 無意識の癖(ブラキシズム):日中の食いしばりや、就寝中の歯ぎしりは、特定の歯や顎の関節に、体重以上の非常に大きな力をかけ続けます。
- 生活習慣:頬杖をつく、いつも同じ側でばかり噛む、うつ伏せで寝る、といった日常の些細な癖が、顎の位置をずらす原因となります。
- 姿勢の悪さ:猫背など、全身のバランスが崩れると、頭の位置がずれ、それに伴って下顎の位置も変化し、かみ合わせに影響を及ぼします。